TOEICを毎月受けることで本当に英語力は伸びるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
「何度も受験しているのに思うようにスコアが上がらない」「モチベーションが続かない」と悩んでいる方も少なくありません。
この記事では、TOEICを毎月受けることで得られる具体的な効果や注意点、さらに効率的な学習方法やおすすめな人の特徴まで、徹底解説します。
毎月の受験が自分に合っているのか知りたい方に役立つ情報をまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。
TOEICを毎月受けることで得られる具体的な効果
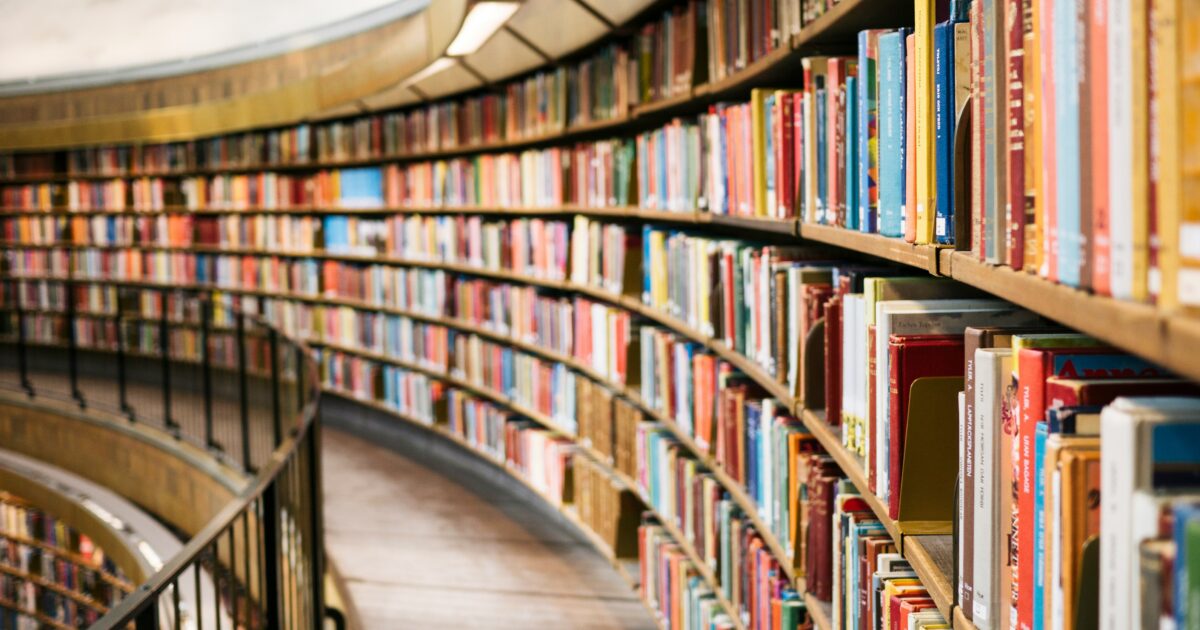
TOEICを毎月受けることで、英語学習の進行や成果に大きな違いが表れるようになります。
継続的な受験は短期間で多くの気づきを与えてくれ、効果的なスキルアップをサポートします。
試験形式や出題傾向への慣れ
毎月TOEICを受けることで、試験独自の形式やパターンに自然と慣れていきます。
リスニングやリーディングの時間配分も体で覚えることができ、本番で戸惑うことがなくなります。
同じような問題や出題傾向に繰り返し触れることで、苦手だったパートにも自信がつきやすくなります。
学習サイクルの最適化
試験前後のルーティンが定着することで、効率的な学習サイクルを築けます。
定期的にテストがあることで「計画→実践→復習→改善」という流れが自然と身につきます。
- 受験後すぐ復習できるので、記憶が新しいうちに弱点を分析可能
- 次の試験までの短期間で改善点に集中して取り組める
- サイクルが早いため、学習リズムが維持しやすい
モチベーションの維持
毎月の試験があることで、「だらけ癖」や中だるみを防ぐことができます。
目標日がはっきりしているため、継続的な学習へと自然に気持ちが向きやすくなります。
「前回より良い点を取りたい」という気持ちが、さらなる努力の後押しになります。
結果からの素早い修正と改善
受験ごとにスコアや間違えたポイントが明確になるため、その都度、学習方法を柔軟に修正できます。
短い間隔で結果が返ってくるので、改善点の把握から対策までがスピーディーに進みます。
| 受験回数 | 学習の修正例 | 効果 |
|---|---|---|
| 1回目 | リスニングが苦手→音読・ディクテーション追加 | 聞き取りやすくなった |
| 2回目 | パート5で時間切れ→短文問題の練習強化 | 時間配分が改善 |
目標達成までのスピード向上
毎月受験を繰り返すことで、学習〜フィードバック〜改善のPDCAサイクルが加速します。
頻繁に成果を振り返れるため、点数アップに向けた具体的なアクションをすぐに起こせます。
長期間ダラダラと取り組むよりも短期間で目標スコアに到達しやすくなります。
本番での緊張感の克服
何度も本試験を経験することで、特有の緊張感に慣れることができます。
試験会場の雰囲気や当日の流れも把握できるので、リラックスして本来の力を発揮しやすくなります。
普段通りの実力を出したい方に毎月受ける方法は特におすすめです。
英語力の成長実感
毎回のスコア変化を見ながら、自身の成長を数値で実感できます。
じわじわと伸びていく点数の推移が、継続学習の大きな励みになります。
苦手だったパートの克服や安定的な高スコアが取れたときに大きな達成感を味わえます。
TOEICを毎月受ける際に注意したいデメリット

TOEICを毎月受験することは、継続的なモチベーション維持や自分の成長を実感できるというメリットがあります。
しかし、その一方で事前に把握しておきたいデメリットも存在します。
ここでは主な注意点について見ていきましょう。
受験料負担の増加
TOEICは1回あたりの受験料が高めに設定されています。
毎月受験することで、1年間にかかる総額が大きくなりやすいです。
例えば、2024年6月時点の受験料は1回7,810円です。
| 受験回数 | 年間合計受験料 |
|---|---|
| 1回 | 7,810円 |
| 6回 | 46,860円 |
| 12回 | 93,720円 |
このように、回数が増えるほど費用負担は大きくなります。
予算を事前に計画し、無理のない範囲で受験スケジュールを立てることが重要です。
勉強の質が下がるリスク
試験に頻繁に申し込むことで、「受けること」自体が目的化してしまうケースがあります。
毎月の試験対策に追われ、じっくりと基礎力を養う時間や計画的な学習が疎かになることもあるでしょう。
- 復習に十分な時間が取れない
- 弱点克服に注力しづらい
- 目標や学習プランがブレやすい
このような状況に陥らないためにも、1回ごとに学習計画を立て、内容の質を大切にしましょう。
点数の伸び悩みへの注意
頻繁に受験していると、点数が思うように伸びない「伸び悩み」を感じる人もいます。
これは、試験と学習のサイクルが短くなりがちなため、弱点を克服する前に次の試験日が来てしまうためです。
さらに、連続で同じような点数が続くとモチベーションが低下しやすくなります。
点数の推移を記録し、「なぜ伸びないのか」を冷静に分析することが大切です。
必要に応じて、受験する間隔を空けるのも一つの方法です。
TOEICを毎月受けるのがおすすめな人の特徴

TOEICを毎月受験することで、自分に合った学習リズムや弱点の把握がしやすくなります。
また、定期的な試験体験により、本番での緊張感にも慣れやすいというメリットもあります。
次に、どのような人に毎月受験が特におすすめなのか、具体的な特徴を紹介します。
短期間で目標スコアを狙う人
限られた期間で目標スコアを達成したい場合、TOEICを毎月受験することで、自分の進捗が定期的に確認できるようになります。
前回の結果をもとに学習内容を調整し、弱点を補強するサイクルが早く回せます。
実際に以下のような流れで学習と受験を繰り返すと、効果的にスコアアップを目指せます。
- 試験を受けて現在地を把握
- 結果をもとに弱点分析
- ピンポイントで対策
- 再び試験で効果を検証
このサイクルを高速回転させることで短期間でのスコアアップが期待できます。
継続的な学習管理が苦手な人
TOEICの勉強は長く続けることが重要ですが、どうしてもモチベーションが続きにくい方もいます。
毎月試験日があることで、「試験を目指して勉強しよう」という明確な目標ができ、サボりにくくなります。
| 学習ペース | モチベーション | 達成感 |
|---|---|---|
| 安定しやすい | 下がりにくい | こまめに得られる |
学習管理が苦手な人にも、毎月のTOEIC受験はペース維持や目標達成につながりやすい方法です。
試験本番で実力を出しにくい人
本番の緊張で実力が思うように発揮できない方は、試験の「場慣れ」を増やすことで成果を出しやすくなります。
せっかく勉強したのに、本番で頭が真っ白になってしまった――そんな経験がある人は、試験を「特別な日」と感じすぎていることが理由かもしれません。
毎月受けることで、試験そのものが日常的なイベントになり、緊張のハードルも自然と下がっていきます。
このように、定期的な受験を重ねていくことで、本来の実力を試験でしっかりと発揮できるようになるでしょう。
TOEICを毎月受ける場合の効果的な学習計画

TOEICを毎月受けることで、試験慣れや英語力の継続的な向上が期待できます。
効果的な学習計画を立てることで、月ごとに確実なレベルアップが目指せます。
成果を感じやすい継続学習のために、計画的な目標設定や復習、模試の活用が大切です。
毎月の学習目標の設定
毎月TOEICを受験する場合、漠然と勉強するのではなく、具体的な目標を設定することが重要です。
たとえば、今月はリスニングパートで10点アップを目指す、単語力を強化する、時間配分の改善に取り組むなど、自分にとって必要なポイントを明確にしましょう。
スコアアップだけでなく、「毎日英単語を50語覚える」「週に2回リーディング問題をこなす」など、行動目標も設定すると継続しやすくなります。
- 具体的なスコア目標を持つ
- 得意・不得意分野を把握し重点を絞る
- 短期・長期の両面で目標を立てる
達成感が定期的に得られるため、モチベーションの維持にもつながります。
復習サイクルの確立
毎月受験するスケジュールでは、効率的な復習がカギになります。
テストが終わった直後に、できなかった問題や間違えたポイントを整理・分析しましょう。
理解が曖昧だった部分をピックアップして、1週間以内に復習するのがおすすめです。
| 復習時期 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 受験直後 | 間違い問題の振り返り | できるだけその日のうちに記録 |
| 1週間以内 | 再度同じ問題に挑戦 | 解き直しで理解が深まる |
| 次回受験前 | 苦手分野の総復習 | 成長を確認しモチベーションアップ |
自分なりの復習サイクルを作ることで、知識が定着しやすくなります。
模試・過去問活用の頻度調整
模試や過去問は実戦力をつけるのに欠かせませんが、毎回同じペースで解くだけでは効率的とはいえません。
月ごとの力試しと、苦手分野の克服という2つの視点から活用の頻度を調整しましょう。
たとえば、模試は月に1〜2回、本番のTOEICの1〜2週間前に集中的に活用すると良いです。
過去問は数回分を事前に確保し、「今月はパート5とパート7を重点的に」などパーツごとの対策にも使えます。
- 本番に合わせて時間を計って取り組む
- 終了後はすぐに自己採点と間違えた箇所分析
- 苦手分野は繰り返し解き直す
- 結果を学習計画に反映させる
模試や過去問を単なる「点数チェック」にせず、学習の柱として効果的に使うことが大切です。
TOEIC毎月受験が向かないケース

TOEICを毎月受けることは、短期間でスコアを伸ばしたい場合やモチベーション維持には効果的な面があります。
しかし、すべての人に適しているとは限りません。
自分の状況や性格によっては、むしろデメリットが大きくなる場合もあります。
ここでは、TOEICを毎月受験するのが向かない主なケースについて解説します。
経済的な負担が大きい場合
TOEICを毎月受ける場合、受験料や会場までの交通費などが毎月かかります。
特に学生や収入に余裕がない方にとっては、この出費が大きな負担となることも少なくありません。
- 受験料(1回6,490円)を毎月支払うと、年間で約78,000円に達します。
- 会場までの交通費や、参考書・問題集などの学習コストも積み重なります。
- 他の資格試験や趣味、日常生活の費用にも影響を及ぼす可能性があります。
経済的な余裕がない場合、一度受験の頻度を見直してみることも大切です。
学習の実施時間が確保できない場合
TOEICのスコアを上げるためには、毎回の受験ごとに新しい学びや復習、弱点の克服が必要です。
しかし、忙しくて学習時間を十分にとれない場合、毎月の受験はあまり意味がなくなってしまいます。
| 受験頻度 | 想定される学習効果 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 毎月 | 学習時間不足の場合、スコアの伸び悩みがち | 低い |
| 2〜3ヶ月に1回 | 十分な学習・復習ができる | 高い |
自分のスケジュールや生活環境を考慮し、無理なく学習時間を確保できる受験ペースを選びましょう。
本番プレッシャーが逆効果な場合
毎月のように本番試験があると、「またすぐに受けなきゃ」と追い詰められる気持ちになる方もいます。
プレッシャーがモチベーションになる人もいれば、逆にストレスや不安が強くなり、本来の実力を発揮できなくなる人もいます。
主な逆効果の例として、以下のようなものが挙げられます。
- 睡眠不足や体調不良を招く
- 一回一回の反省や分析が不十分になる
- 試験当日ミスが続き、自己肯定感が下がる
無理に毎月受け続ける必要はありません。自分に合った頻度で受験し、前向きな気持ちで学習に取り組めるようにしましょう。
TOEICを毎月受ける選択で満足できる人の共通点

TOEICを毎月受験して満足している人にはいくつかの共通点が見られます。
まず、目標スコアが明確な人は毎月受験のメリットを実感しやすいです。
定期的な受験が「英語力維持の仕組み」になり、計画的に学習を続けられるタイプです。
また、継続して学習できるモチベーションの高い人も満足度が高い傾向があります。
毎月結果が返ってくることで、小さな成長や課題をすぐ振り返ることができ、次への改善点につなげています。
就職や転職、社内評価など、スコアアップに直結した明確な目的を持つ人も、毎月受けることで手応えを感じやすいです。
さらに、「失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢」がある人も、毎月の受験を習慣化できて満足度が高い特徴です。
時には思うような結果が出なくても、「次がある」と前向きに捉えやすいです。
一方で、コストや時間の管理がしっかりできる方が多いのも特徴です。
限られた時間の中でTOEIC学習を日常生活に組み込み、受験費用も投資と割り切れる柔軟な考え方を持っています。
このように、目標・モチベーション・計画性など、いくつかの共通点を持つ人は、TOEICを毎月受けることで大きな満足感を得やすい傾向があります。

