「TOEICの新形式と旧形式の違いがいまいち分からなくて不安」と感じていませんか。
テスト形式の変更は多くの受験者に戸惑いを与え、どんな対策が必要か悩む方も多いでしょう。
本記事ではTOEIC新形式と旧形式の具体的な違いや背景、効率的なスコアアップのコツまで、わかりやすく解説します。
リスニングやリーディングの変化、最新の出題傾向、新形式ならではのポイントも押さえているので、混乱することなく対策に集中できます。
TOEIC新形式による変更点や学習法を知り、スコアアップにつなげたい方はぜひ続きもご覧ください。
TOEIC新形式と旧形式の違いを徹底解説

TOEICは2016年から新形式に変更され、従来の問題構成や出題傾向が大きく見直されました。
ビジネスシーンでより実践的な英語力を測るため、リスニング・リーディングともに内容がアップデートされています。
新形式を理解することで、より効果的に試験対策を進めることができます。
リスニングセクションの主な変更点
リスニングセクションでは、パートごとの問題数や出題パターンに調整が加えられました。
特にパート3とパート4では、複数人による会話や図表参照といった新しい問題タイプが追加されています。
旧形式では一人の話者同士のやりとりが多かったのに対し、新形式では複数人が登場し、やや複雑になりました。
音声のスピードやアクセントパターンも多様化しています。
- 設問数の増減
- 意図問題や図表参照問題の追加
- 複数人の会話への対応
リーディングセクションの主な変更点
リーディングセクションでも、パートごとの問題数と内容に変化がありました。
特にパート6とパート7で大きな違いが見られます。
パート6では従来の文法穴埋め問題に加え、文挿入問題が新たに登場しています。
パート7では「トリプルパッセージ」と呼ばれる3つの関連文書を読み解く問題が加わり、ボリュームが増加しています。
また、eメールや広告など、より日常的な英文素材が多く使われるようになったのも特徴です。
問題数やパート構成の違い
新形式では全体の問題数は変わりませんが、パートごとの内訳が変化しています。
リスニングでは、一部のパートで設問数が増減しています。
リーディングでは、特に長文読解のパートで問題数が増え、文挿入問題が加わりました。
| セクション | 旧形式 | 新形式 |
|---|---|---|
| リスニング総問題数 | 100問 | 100問 |
| リーディング総問題数 | 100問 | 100問 |
| 長文読解(パート7) | 48問 | 54問 |
| 文挿入問題 | なし | 追加 |
| トリプルパッセージ | なし | 追加 |
出題傾向の変化
新形式では、より実践的な英語運用力を測る方向へシフトしています。
会話や文章の背景や意図を問う設問、図やグラフとセットになった設問が増加しました。
また、英語の聞き取りや読解において、よりさまざまなシチュエーションや表現が使われるようになっています。
語彙やリスニングスキルだけでなく、論理的な理解力や情報整理能力が重視されるようになった点も大きな特徴です。
難易度の体感の変化
新形式では試験の難易度が一律に上がったわけではありませんが、変化に戸惑いを感じる受験者も少なくありません。
特にパート3やパート7で新しいタイプの問題が増えたため、慣れが必要になりました。
一方で、日常的な英語力や読解力をもともと持っている人にとっては、学習の成果がスコアに反映されやすくなったとの声もあります。
新形式で追加された問題タイプ
TOEIC新形式では、いくつかの新しい問題タイプが登場しました。
- 図表やスケジュール表を参考にしながら答える問題(リスニング、リーディング両方)
- 複数名の会話を聞いて状況を判断する問題
- 発言の意図や気持ちを問う設問
- 文章の適切な位置に文を挿入する文挿入問題
- 三つの文書をまとめて読んで答えるトリプルパッセージ問題
これらの新設問題は、実際のビジネス現場や日常生活で役立つ英語力を養うために工夫されています。
新形式の特徴を理解し、早めに対策を始めることで高得点を狙うことができます。
TOEIC新形式導入の背景・意図

TOEICは国際的に通用する英語コミュニケーション能力を測定するテストとして、多くの企業や教育機関で利用されています。
時代の変化に合わせて英語使用場面が多様化している中、TOEICもその実態にマッチするように問題形式の見直しが行われました。
新形式への移行は、現代のグローバルなコミュニケーションに必要なスキルをより適切に測るための取り組みといえます。
変更された時期
TOEICの新形式は2016年5月から日本で導入されました。
この時、全世界で順次新しい問題形式へ移行が実施されました。
旧形式での試験を受けていた受験者にとっては、2016年を境に出題傾向や問題のバリエーションに大きな変化がありました。
| 導入時期 | 対象地域 |
|---|---|
| 2016年5月 | 日本 |
| 2016年6月以降 | 他の国・地域 |
改訂の理由
TOEICの形式改訂が行われた主な理由は、現代のビジネスシーンや日常生活で必要な英語力をより正確に評価するためです。
従来よりも発言者や場面の多様性が増し、複数人による会話や図表の読み取りが問われる形式が増えました。
このことにより、より実践的な英語運用能力が試されるようになりました。
- リスニングでは複数人の会話が導入
- リーディングでは1つの設問で複数文書を読むパートが追加
- グラフィック(図表)を用いた設問の強化
ETSの意図
TOEICの開発元であるETS(Educational Testing Service)は、グローバル化が進む現代社会において必要とされる英語力にフォーカスすることを新形式導入の大きな意図としています。
実際の職場や日常会話で求められる英語運用力を測定し、受験者に現実的な英語スキル向上を促すことが目標です。
また、多様化するビジネスシーンでのコミュニケーション能力をより明確に反映できるよう、設問内容や形式自体を最適化しています。
新形式TOEICで高得点を狙うための対策

新形式のTOEICでは、従来とは問題の傾向や構成が変化しています。
そのため、旧形式での勉強法だけでは高得点を取るのが難しくなりました。
ここからは、リスニングとリーディングそれぞれの適応方法、そして時間配分のコツについて解説します。
リスニングへの適応方法
新形式のリスニングでは、様々な国の英語アクセントや複数人による会話が増えています。
知らないアクセントにも慣れるため、イギリス英語やオーストラリア英語の音声教材を活用すると良いでしょう。
また、会話問題が増えたことで、話の流れや発言者の意図を素早く捉える力が求められます。
- 複数人の会話練習を取り入れる
- 本番形式の音声でシャドーイングを行う
- 問題文と選択肢を先読みし、話の全体像を意識する
パートごとに特徴が異なるため、各パートに応じた対策も欠かせません。
| パート | 変化点 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| パート1 | 写真描写問題の数が減少 | イメージから文脈を想像する練習 |
| パート3/4 | 複数人会話や図表の参照が増加 | 図表と会話内容をリンクさせる訓練 |
リーディングへの適応方法
新形式のリーディングでは、複数文書問題や語彙・文法の出題傾向に変化が見られます。
特に、複数の英文を読み比べて答えを選ぶ設問が増加しています。
これに対応するためには、文書ごとの関連性や、文中の情報を速く正確に読み取る練習が大切です。
語彙問題はより実用的な表現が多くなっているため、頻出のコロケーションやパラフレーズに注意して取り組みましょう。
また、文法問題も形式的な知識だけでなく、意味や文脈を把握して解く力が必要です。
公式問題集を繰り返し解いてパターンに慣れることがスコアアップの鍵となります。
時間配分の工夫
リーディングセクションは特に時間内にすべての問題を終わらせることが難しくなっています。
新形式では問題数や分量が増加しているため、事前に時間の目安を把握しておきましょう。
| パート | 推奨解答時間(分) | ポイント |
|---|---|---|
| パート5 | 10~12 | 素早く解き、一つの問題にこだわらない |
| パート6 | 7~8 | 前後の文脈を重視 |
| パート7 | 50~53 | 問題によっては後回しにする柔軟さも必要 |
各パートごとに時間を意識しつつ進めていけば、最後まで問題に取り組むことができるようになります。
実際の試験を想定した模試やタイマーを使った練習が効果的です。
TOEIC新形式で役立つ教材・学習リソース
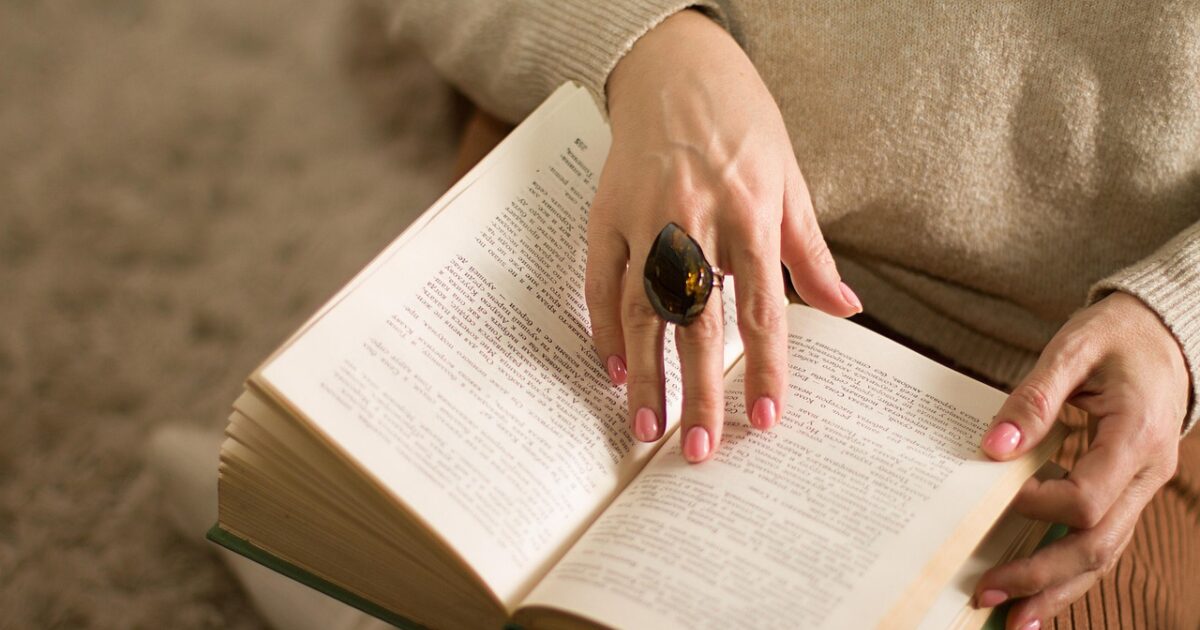
TOEICの新形式に対応するためには、適切な教材や学習リソースを活用することが大切です。
新形式特有の問題や傾向を把握し、効率的にスコアアップを目指しましょう。
ここでは、特に役立つ教材や選び方のポイントを紹介します。
新形式対応の問題集
新形式にしっかり対応した問題集を使うことで、実際の試験に近い形で練習ができます。
リスニングやリーディングの形式が変わった部分を重点的に学習できるものがおすすめです。
特に人気の高い新形式対応の問題集は次の通りです。
- 『公式TOEIC Listening & Reading 問題集』シリーズ
- 『新TOEICテスト出る順で学ぶボキャブラリー990』
- 『TOEIC L&Rテスト パート別問題集』
これらの問題集は新形式の問題を数多く収録しており、パートごとの練習にも最適です。
公式模試の活用
本番前の実力チェックや時間配分の練習には、TOEIC公式模試が非常に役立ちます。
実際の試験形式にそっくりなため、模試を繰り返すことで本番への自信と安定した実力が身につきます。
| 教材名 | 特徴 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| TOEIC公式問題集 | 最新の本試験と同じ難易度 | 実践的な模擬テストで弱点発見 |
| TOEIC公式オンライン模試 | 自宅で受験できる | 本番環境を再現しやすい |
模試の結果を振り返り、自分の苦手なパートを重点的に復習することが大切です。
参考書の選び方
新形式に対応する参考書を選ぶときは、内容が最新の出題傾向を反映しているかを確認しましょう。
図解や解説が充実していて、はじめて受験する方でも理解しやすいものが良いです。
選び方のポイントは以下の通りです。
- 表紙や目次で「新形式対応」と明記があるかをチェック
- 分野別・パート別など、自分の弱点に合わせて選ぶ
- 口コミやレビューで実際の使いやすさを参考にする
自分の学習スタイルに合った参考書を選ぶことで、効率よく対策を進めることができます。
TOEIC新形式と旧形式の違いを正しく理解して効率よくスコアアップするために
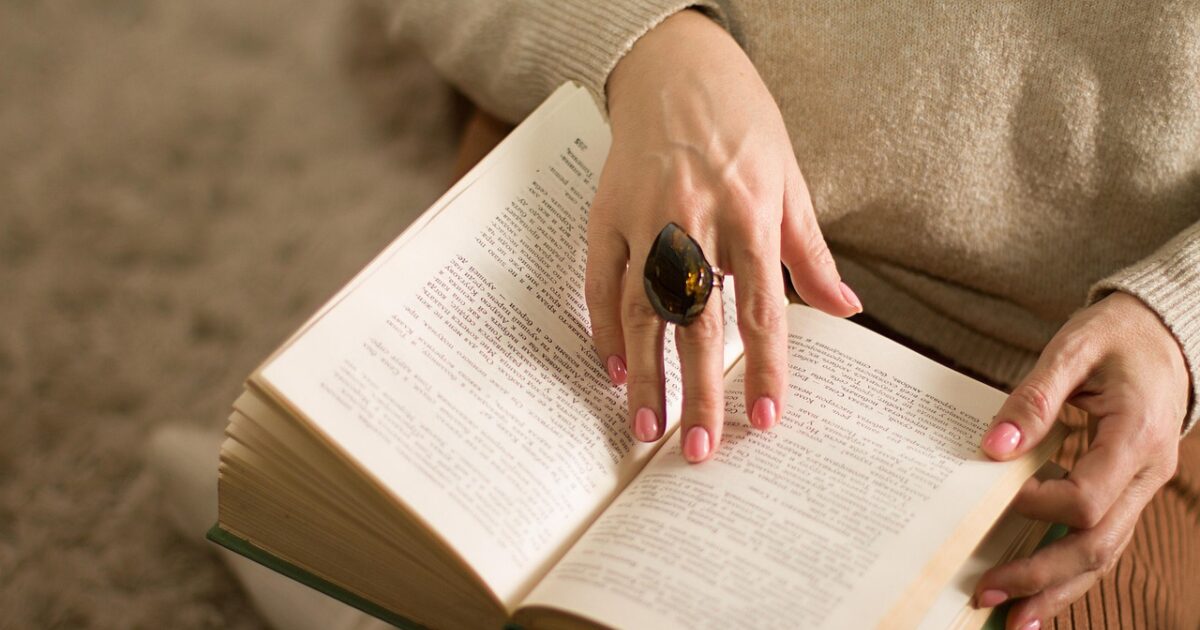
TOEICの新形式と旧形式にはいくつかの大きな違いがありますが、これらを押さえておくことで無駄な勉強を減らせます。
まず、新形式ではリスニングとリーディングパートの両方で出題傾向に変化がありました。
リスニングパートでは、写真描写問題の数が減り、会話文中に3人の話者が登場する問題が加わった点が特徴です。
また、図や表を見て解答する設問の導入により、情報整理力も重要になりました。
リーディングパートでは、語彙や文法問題が削減され、複数文書を扱うマルチパッセージ問題が増加しました。
これにより、単なる文法知識だけでなく読解力や情報を比較・統合する力が問われるようになっています。
新形式の変更点を正しく理解することで、どのパートに重点を置いて対策すればよいかが明確になります。
旧形式の対策教材だけで勉強を進めてしまうと、不足しがちな新傾向問題への練習が不十分になる可能性が高いです。
最新版の公式問題集など新形式に準拠した教材を使って繰り返し練習することが、着実なスコアアップへの近道と言えるでしょう。

