TOEICの新形式が導入されてから、「今までより難易度が上がったのでは?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
リスニングやリーディングの手応えが変わり、スコアにも影響が出ていると不安を感じている方も少なくありません。
この記事では、TOEIC新形式の難易度がどう変化したのかを、実際の傾向や受験者の声、さらには具体的なパート別の特徴など、徹底的に解説します。
また、スコアアップに直結する対策や学習法も紹介し、今後TOEIC新形式の受験を考えている方が自信を持って取り組めるヒントをお伝えします。
今のTOEIC新形式について本当の難易度やその乗り越え方を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
TOEIC新形式の難易度は実際にどう変わったのか

TOEICは2016年に大幅な出題形式の変更が行われました。
新形式への切り替えは、多くの受験者にとって気になるポイントです。
特に、どのセクションで難易度が上がったのか、またスコアへの影響はどの程度あるのかが注目されています。
ここでは、TOEIC新形式の難易度の変化についてセクションごとに詳しく見ていきます。
全体的な難化傾向
新形式では、全体的に問題の種類や傾向が洗練され、実際のコミュニケーションに近い内容になりました。
その結果、従来のパターン学習だけで高得点を狙うのが難しくなったと言われています。
特に、情報処理速度や実践的な理解力が求められる傾向が強まりました。
実際、多くの受験者から「問題を解くスピードがさらに重要になった」という声が聞かれます。
リスニングセクションの難しさの変化
リスニングでは、導入された新しい設問や形式が難易度を上げています。
たとえば、写真描写問題が減少し、会話や説明文の内容理解が重視されるようになりました。
また、会話の人数が増えたり、自然なイントネーションやアクセントの英語が聞かれるようになりました。
- 複数人の会話(パート3)で誰が発言したのかを見極めるスキルが必要
- 図や表を参考にしながら聞く問題が追加された
- 情報を素早く選択・判断する力が求められる
こうした要素によって、リスニングセクションの対応力が全体的に試されるようになっています。
リーディングセクションの難易度変化
リーディングでも、以前より複雑な文章や複数文書を読む問題が増えました。
特に、パート7のダブルパッセージに加え、トリプルパッセージが新登場しています。
| 旧形式 | 新形式 |
|---|---|
| シングルパッセージ中心 | ダブル・トリプルパッセージが増加 |
| 設問も比較的単純 | 設問がより複雑で長文に |
| 短文穴埋めが多め | 実用的な文脈の理解が重視 |
また、文書同士の関連性を素早く読み解く読解力、複数の設問で情報を整理する力が必須になりました。
新形式で追加された問題タイプの影響
新形式では、図表を見ながら答える問題や、3人以上による会話問題、新しい選択肢の提示などが導入されています。
こうした新問題タイプによって、単純な暗記やパターン化した学習だけでは対応しきれない場面が増えました。
具体的には、以下のような影響があります。
- 臨機応変な判断力の養成が重要になった
- より実践的な英語コミュニケーション力が評価される
- 従来より時間配分が難しくなった
従って、従来の形式と比べて、多様な問題へ幅広く対応する総合力が求められます。
スコアへの影響
新形式への移行直後は「スコアが取りにくくなった」と感じた受験者も少なくありません。
ただし、スコア換算の仕組みには大きな変更がないため、全体としてスコア分布は大きく崩れていない傾向です。
とはいえ、問題そのものの難易度や、試験への慣れ度合いがスコアに影響するケースも多く見られます。
従来よりも高得点を目指すには、新形式で強化された能力を意識した対策が不可欠でしょう。
受験者の体感・評判
実際に新形式TOEICを受験した方々の評価はさまざまです。
多く聞かれる主な声には次のようなものがあります。
- 全体的に「難しくなった」との声が多い
- 「時間配分に苦しんだ」という体感が増えている
- 「より実践的な英語力が必要」と評価する声も多い
- 逆に「問題のバリエーションが増えてやりがいを感じた」という肯定的な意見もある
このように受験者によって体感や評判は異なりますが、以前に比べて対応力や実力本位の試験へ進化していると受け止める方が多いようです。
TOEIC新形式で難易度が上がった主な理由

TOEICが新形式になったことで、多くの受験者が以前よりも難しくなったと感じています。
これにはいくつかのはっきりとした理由があります。
各設問の内容や出題傾向が見直され、スコアを上げるためにはより幅広いスキルが求められるようになりました。
設問パターンの多様化
新形式では設問のパターンが多様化し、問題ごとの出題意図が分かりにくくなりました。
以前のようにパターン化された解き方だけでは通用しないケースも増えています。
- 選択肢の紛らわしさが増加
- 正しい情報を素早く取捨選択する力が必要
- 日常的な英語利用の場面設定が多い
このようにさまざまな設問が出るようになったことで、短時間で情報を整理する力がより重要になっています。
英文量の増加
新形式では英文量が全体的に増加しています。
とくにリーディングセクションにおいて長文問題が増え、読むべき文章が多くなりました。
読解スピードが求められると同時に、内容を正確に理解する力も問われます。
| 形式 | 1パッセージあたりの語数 |
|---|---|
| 旧形式 | 約250語 |
| 新形式 | 約350語 |
この変化により、時間配分に悩む受験者が増えています。
図表・グラフ問題の導入
新形式では、図表やグラフを使った問題が加わりました。
これらの問題では、英文と図表やグラフの情報を同時に理解し、答えを導き出す必要があります。
ただ英文を読むだけでなく、視覚的な情報も素早く読み取るスキルが求められるため、難易度が上がったと感じる人が多くなりました。
自然な英語表現の増加
新形式の問題では、より自然な英語表現や会話が多くなっています。
これまでは見慣れた表現や堅い英語が多かったのが、実際の生活やビジネスで使われる生きた表現に変わっています。
そのため、英語を実用的に理解する力がますます重視され、耳慣れない表現が出ることも増えています。
パート別のTOEIC新形式の難易度
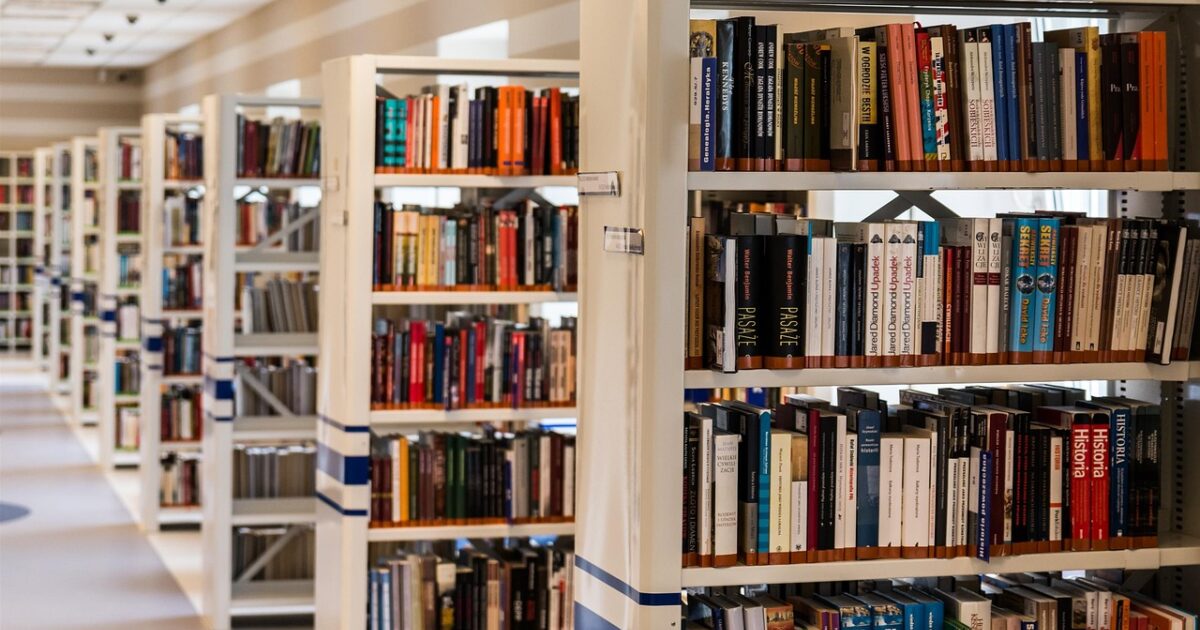
TOEICの新形式は、従来の形式に比べて全体的にリスニング・リーディングともに実践的な英語力がより幅広く問われるようになりました。
特にパートごとに特徴があり、難易度の感じ方も人それぞれです。
ここでは各パートごとの難易度について詳しくご紹介します。
Part1の難易度
Part1は写真描写問題で、難易度としては全パートの中でも比較的易しい部類に入ります。
ただし新形式では、これまでになかった写真や行動が描写されることも増え、細かな観察力や、普段聞き慣れない表現が求められることもあります。
以前より設問数が減った分、一問ごとの重要度も増しているため、うっかり聞き逃さない注意が必要です。
Part2の難易度
Part2は応答問題で、短い会話文のやりとりを聞いて答える形式です。
新形式ではわざと「間接応答」や「質問返し」のパターンが増えており、単語だけで即答できない問題も多くなりました。
- 答えが直接的ではないパターンがある
- 意図を推測する力が必要になる
- 選択肢同士の意味が似ていることが多い
全体として、以前よりも少し難易度が上がったと感じる受験者が多いです。
Part3の難易度
Part3は会話問題で、複数人でのやり取りや図表を参照する新傾向問題が特徴的です。
特に新形式では、3人で話す場面やグラフィック(図や表)を見ながら解く問題が追加され、情報を同時に処理する力が問われます。
| 特徴 | 難易度のポイント |
|---|---|
| 3人会話 | 話者の位置や発言者を把握する力が重要 |
| 図・表参照 | 英文と資料を同時に見る読解力が求められる |
| 早い会話の展開 | 話の流れをつかむ集中力が必要 |
これまでよりも実践的な英語力が試されるため、慣れていないと難しいと感じやすいパートです。
Part4の難易度
Part4は1人の話者による説明や案内を聞き取り、質問に答える形式です。
新形式では、グラフィック問題が導入され、聞きながら図や表の内容も確認する必要があります。
一度しか流れない放送を正確に捉え、必要な情報を聞き取りながらメモを取るスキルや読解力がポイントとなります。
やや難易度は上がったと言えるでしょう。
Part5の難易度
Part5は短文穴埋め問題で、語彙力や文法力が問われます。
新形式でも基本的な形式は変わりませんが、選択肢の紛らわしさや複数の正答パターンが増えた影響で、素早い判断力が求められるようになりました。
特に難易度が上がったということはありませんが、時間配分に気をつける必要があるパートです。
Part6の難易度
Part6は長文穴埋め問題で、文や段落自体を選択して埋める新形式も導入されています。
これにより、文脈をより深く理解し、ロジカルに流れを考える力が重要になりました。
文挿入問題は一見難しそうですが、慣れればパターン化して対処できる内容も多いです。
全体として、リーディング力の底上げが必要なパートといえます。
Part7の難易度
Part7は長文読解問題で、シングルパッセージ、ダブルパッセージに加えてトリプルパッセージが加わったことで難易度が大きく上がりました。
複数の文書を行き来しながら関連性を見抜き、必要な情報を速く正確に拾い上げる力が試されます。
また、Eメールや広告、記事などさまざまな文書形式が登場するので、実務的なリーディング力が問われます。
新形式になってからは、パート7が最も難しいと感じる受験者が多くなっています。
TOEIC新形式の難易度対策に有効な学習法

TOEICの新形式では、出題傾向や問題構成が変わったことで、従来よりも多角的な英語力が求められるようになりました。
しっかりと対策を立てて取り組むことで、点数アップが期待できます。
ここでは、新形式で高得点を狙うために役立つ学習法をご紹介します。
最新傾向問題への慣れ
TOEICの新形式では、リーディングとリスニングの両セクションで設問パターンや出題内容が刷新されています。
特に写真描写やチャット、メールのやり取りなど今まで見られなかった形式が増えています。
最新の問題傾向に慣れるためには、以下の方法が効果的です。
- 公式問題集や最新の模試問題に積極的に取り組む
- 実践形式の演習を通し、時間配分の感覚を養う
- 出題されやすいパターンを分析・復習する
これらを繰り返すことで、試験本番でも落ち着いて対応できるようになります。
リスニング力強化のトレーニング
リスニングセクションの難易度は、話者のアクセントが多様になり、実践的な英語力が問われるようになっています。
イギリス、アメリカ、オーストラリアなど複数の国の発音を聞き取れるようになることが重要です。
| トレーニング方法 | ポイント |
|---|---|
| 公式問題集を使ったリスニング演習 | 実際の音声になれる |
| シャドーイング | リスニングと発音を同時に強化 |
| 海外ニュースやポッドキャスト視聴 | 多様なアクセント・表現に触れる |
毎日短い時間でも継続することがコツです。
長文読解力の養成
新形式では長文のボリュームが増え、一度に大量の情報を処理する力が必要です。
複数のメールやチャット、広告などを読み比べて解答を導く問題も目立っています。
読解力を養うためには、次のような方法が効果的です。
- 時間を計って長文問題を解く練習を積む
- 文章構造や要点を素早く把握する読解テクニックを身につける
- 毎日英字記事やコラムを読む習慣を作る
量をこなすことが強い読解力につながります。
ボキャブラリー強化
TOEIC新形式では語彙力も重要視されています。
会話やメール、広告で使われる実用的な単語やイディオムも頻出です。
単語帳だけでなく、実際の問題を使って意味や使い方を覚えていきましょう。
重要単語の復習や派生語、同義語のセット学習もおすすめです。
語彙力の底上げが総合得点アップに直結します。
これからTOEIC新形式を受験する人へのアドバイス
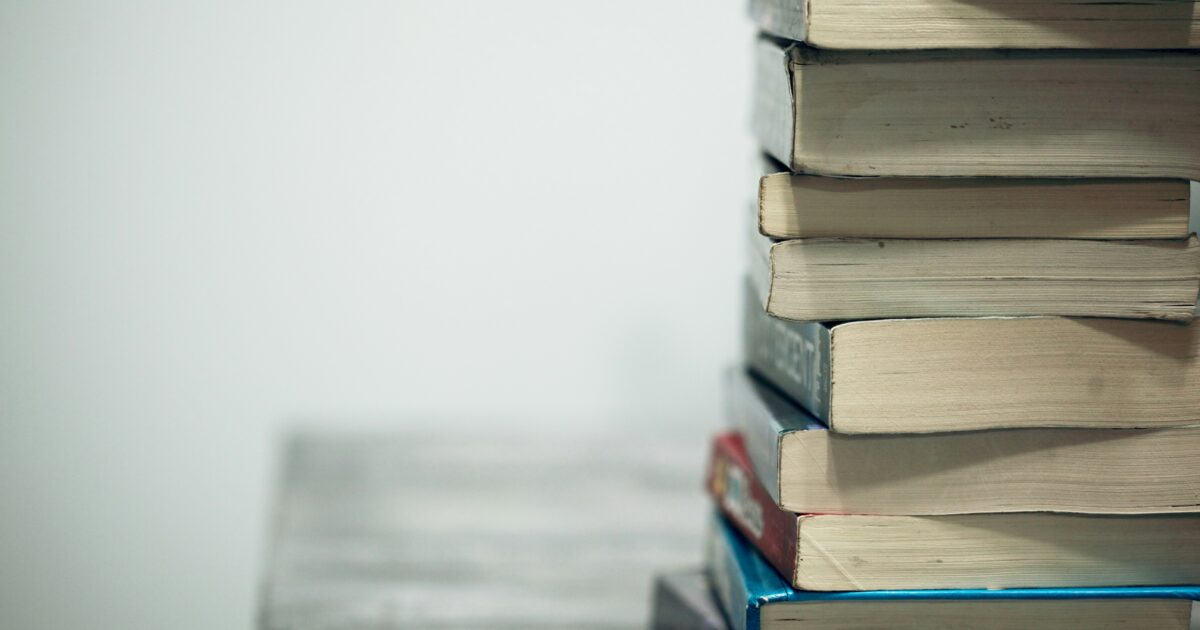
TOEICの新形式に挑戦する際には、従来の形式との違いや難易度の変化にしっかりと対応することが重要です。
初めて受験する方や久しぶりに受験する方は、勉強方法や意識するポイントを押さえておくことで、効率的にスコアアップを目指せます。
演習量の確保
新形式のTOEICでは、従来よりも語彙や文法だけでなく、実践的な英語力が求められます。
演習問題に数多く取り組むことで出題パターンや設問の傾向に慣れ、得点源を増やしましょう。
計画的に毎日少しずつ問題演習を積み重ねることが、リスニング、リーディング両方の対応力向上につながります。
よく出る形式の問題だけでなく、苦手なパートもバランス良く演習することがおすすめです。
- リスニングは毎日音声を聞いて耳を慣らす
- 長文やグラフ問題などさまざまなタイプのリーディングにも挑戦する
- 間違えた問題は必ず見直して復習する
模試の活用法
本番さながらの模試を定期的に解くことで、自分の現在の実力や弱点が明確になります。
模試はTOEIC新形式に対応したものを選び、必ず時間を計って取り組むことが大切です。
解いた後は自己採点を行い、間違えた箇所や、迷った問題を中心に復習をしましょう。
また、模試は試験直前だけでなく、定期的に活用して自分の上達度を測ることがポイントです。
| 模試の活用法 | 効果 |
|---|---|
| 時間を測って解く | 本番と同じ緊張感で取り組むことができる |
| 間違いの分析 | 苦手分野を発見できる |
| 定期的な実施 | 実力の伸びをチェックできる |
時間配分への意識
TOEIC新形式は試験時間が限られているため、各パートごとの時間配分が重要になってきます。
特にリーディングセクションは最後まで解ききれない受験者も多く、時間が足りなくなる傾向があります。
事前にパートごとの目標時間を決めておくことで、焦らずに試験に取り組めます。
練習の段階から意識して制限時間内に解くトレーニングを重ねておくことが大切です。
TOEIC新形式の難易度総括と今後の展望
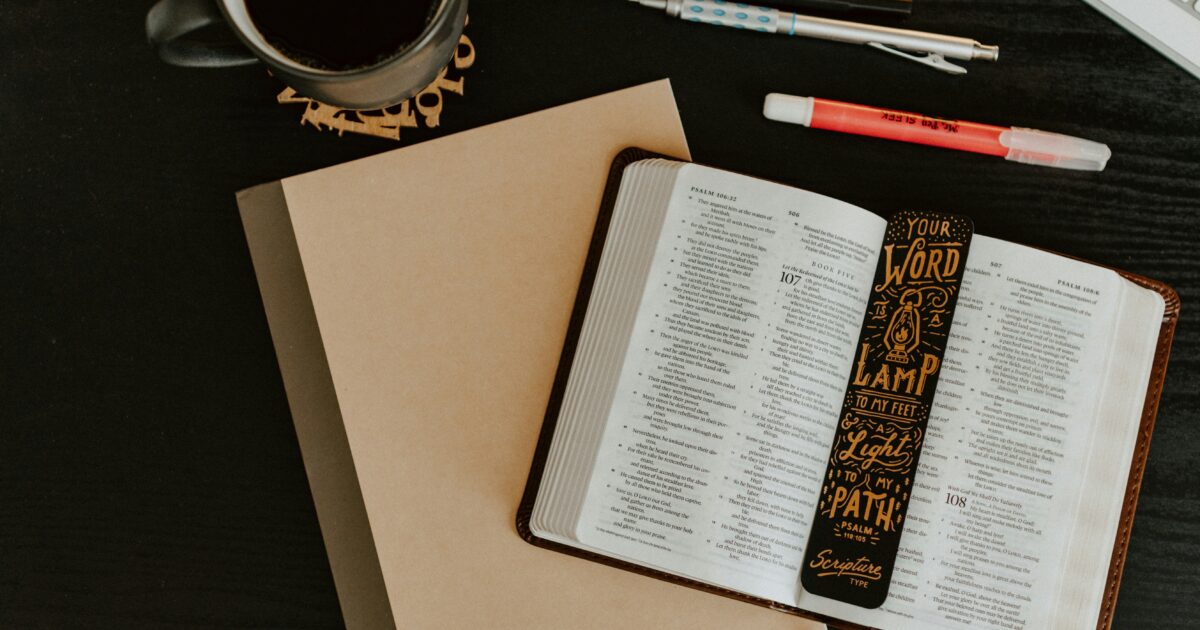
ここまでTOEIC新形式の特徴や各パートの難易度についてご紹介してきました。
新形式では、リーディングやリスニングの設問内容に変化があり、これまでの勉強法を見直す必要がある受験者も多くなっています。
特に複数人会話や写真描写など、実際のビジネスシーンに近い問題が目立つため、総合的な英語力がより問われるようになったといえるでしょう。
一方で、傾向を知り対策を行えば、決して手の届かない難易度ではありません。
今後の展望としては、コミュニケーション力重視のトレンドがさらに強まることが予想され、暗記だけではなく実際に使える英語を身につける学習の重要性が高まります。
今までのTOEICの対策に加え、時事英語や表現の幅を広げるトレーニングも効果的です。
新形式のポイントを押さえて計画的に学習を進めることが、これからのTOEICで高得点を目指す近道となるでしょう。
自分の弱点や現在のレベルをしっかり見極めつつ、焦らずコツコツと力を積み重ねていくことが、新形式TOEICを攻略する鍵です。

